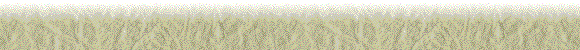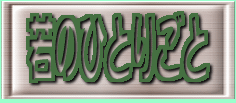

7月31日(火)
あっという間に今月も終わってしまいました。 また暑さが戻ってきまして、仕事が終わってからの30〜40分程の屋外プールが堪らなくいい気持ちです。
「いい気持ち」と言えば「四人囃子」の『おまつり』ではありません、夕方ではないですし。 お馴染みの『夜ヒット』で『E気持ち』を歌ったヒロくんが出てました(でも記憶にない二曲目らしきものを歌ってましたけど)。 それよりか『燃えて パッション』を歌った堤大二郎さんが「ああ、いたいた」という気持ちにさせてくれました。 スクールメイツの皆さんも頑張ってました。
土曜日に暑くて髪を切りに行きましたが、あの方もこの週末でちょっとシャギーを入れたみたいです(あのままでもよかったのに)。
今朝は当店の並びの「ナイルレストラン」が取材されてました(もちろんレポーターによる録画でしたが)が、冷たいレトルト・カレーが出るそうです。 その試食を本場の人にやってもらったということなのですが、あのマスターは、とっても歌舞伎通でして、台詞もすらすらと言えたりしますので驚いちゃいます。 いつも並んでますので、並ぶのが嫌な私は行ったことがありません。
そんな私でも10人くらい並んでいるJRのみどりの窓口に切符を買いに行きました。 よくあるんですけど、自分の番になってからああだこうだと悩むん人がいます。 並んでいる間は何してたんだと、イライラしながらやっとのことで自分の番になって、さっさと買ったはいいのですが、午前と午後を間違えてしまい、もう一回並びなおすという間抜けなことをやってしまいました。 元・鉄道ファンだったくせに・・・。
7月30日(月)
大正末あたりから昭和二桁になったくらいまででしょうか、創刊当時は「活動写真」と言われていた「映画」と歌舞伎や新派、レビューなどを総括した「演劇」を一緒に掲載した月刊誌が多く発行されました。
題名は『芝居とキネマ(←さすがは大正時代)』『映画と演芸』『演芸と映画』『演芸と映画界』『劇』など、ちゃんと調べたことがないので、全部が独立した雑誌なのか否かということも判りません(一応「映画専門店」ではないので・・・)が、内容はどれも似たり寄ったりです。
体裁は『アサヒグラフ』の増刊として出されたものは同じ縦の大判という大きさですし、それより一回り小型のものや、横長のものあったりします。
ですので、全部が独立したものとすれば、権利もへったくれもない無差別化の雑誌ですので、長続きしなかったのは食いつぶししあったのでしょうか、時代による統廃合の結果なのでしょうか、兎に角10年代に入るまでにほどんど消えてます。 題名は忘れましたが、中には昭和17年くらいまで続いたものもありました。 また『映画と演芸』は戦後に復刊され30年代にも生き続いてました。
話は長くなりましたが、そうした雑誌は行くところに行くとべらぼうに高かったりして昔はなかなか手が届きませんでした。 ところがギッチョンチョンでございます。 この仕事のお陰で市場で多く見ることが出来るようになりました。 場合によっては買ってきてお店に置くこともあります。 ってなてなもんで侍れけれ、今回も買いました。
この手の雑誌はよく切り取られていることが非常に多いので、隅々までチェックをしないといけません。 そうしてパラパラ見ていると、自分の知らない作品(特に映画)に驚かされることがあります。 で、今回は久々にありました。 それも自分の中では本当に驚きでした(その人に興味がないから「知らなかっただけ」ですまないんじゃないかと思います)。
題名は『デパートの姫君』、あ、まず時代ですね、『映画と演芸』昭和7年2月号です。 主演は、何と「栗島すみ子」、大正末の松竹蒲田を代表するアイドルです。 確かに小津安二郎監督作品『淑女は何を忘れたか(昭和12年)にも出てますから現役だったんでしょうけど、おばさんでしたからねぇ。
キャプションにはこう書かれてありました。 「池田義信監督、栗島すみ子主演のモダーネスそのものゝ様な現代物。すみちゃんの洒落た姿」・・・確かにどこかの百貨店で買った大きな箱を3つ4つ重ねて持って、お澄まししています。 帽子なんかかぶって。 昭和7年でPCLが無いから伏見信子っていうわけにはいきませんけど、日活だったら市川春代ですね、だけど顔は、いっくら頑張ってもおすみさんなんですよねぇ。
またもう一枚の写真に一緒に写っているのが「ベニ子」役の『マダムと女房』でお馴染みの伊達里子(註1)ですから、先が見えてます。 PCLが出来るまでの日活現代劇のモダーンさには蒲田調は勝てませんよ、バタ臭い方の小津作品あたりじゃないと(註2)。 でもタイトルは結構いいのがあるんですよね、映画史にはまったくもって引っかからないんですけど。
同じ号に載っていただけでも『女は袂を御用心(成瀬巳喜男監督・小倉繁主演)』とか『夜はお静かに』とか『春は御婦人から(これは小津作品)』、日活はというと、『笑っちゃいやよ(市川春代主演)』くらいです。 こちらは時代劇も盛んでしたから、この年の正にこの号に、あの伊丹万作監督の『国士無双(片岡千恵蔵主演)』が載ってます。
いやぁ、映画って本当にいいもんですねぇ。 私にとってこの言葉は使うことがありませんでしたけど、この当時に生まれていれば、連発してたでしょうね。
(註1)この頃の松竹モダーン不良チック映画には欠かすことのできない人。
(註2)『その夜の妻(昭和5年)』とか『非常線の女(昭和8年)』とか、伊達里子も出ているのなら『朗らかに歩め(昭和5年)』なんかも。
7月29日(日)
隅田川の花火大会も事件に発展するようなことも起きず無事終わりました。 住まいから2〜300メートル行った所が清澄通りですが、浅草方面に向けて1キロくらいでしょうか、直線の所があるんです。
そこから見ると、丁度道の真中で花火が大きな弧を描いてキレイです。 両脇はビルなんですけど。 道路の高さが丁度いんでしょうね。 もっと先に行ったとしてもダメなんです。 穴場って言やぁ穴場なのでしょうか。
花火と言えば「大川興業」ですが、ここ数年『ぴあ』を買いませんが、彼の連載記事ってまだやっているんでしょうか? 毎回借金を載せてたやつです。 付き合いで一度だけライヴに行ったことがありましたが、いつだったかなぁ・・・、兎に角まだ実家にいた頃ですから、6〜7年は前でしょうか。 それなのに今だにDMが実家に届いてます。 あの時に一緒に行った人が「これはプレミアがつく」って言ってCDを買いましたけど、どうなったのでしょうか。
7月27日(金)
明日は隅田川の花火大会です。 2〜3日前のような気温だったらとか、台風が直撃したらっとかいう心配はないみたいなので、気持ちよく見る事ができるのではないでしょうか。
隅田川の花火といったら、亡くなった漫才の「桂子・好江」の好江師匠です。 いつも3月10日のことを番組で言ってました。
「桂子・好江」と言えば、以前は浅草演芸ホールの「余一会(註)」に行ってましたが、こっちは暇で昼頃から一番前の真中にいるもんですから、芸人さんの客いじりの対象にさせられました。
桂子師匠に「奴さんを知ってるか?」って片言の英語で聞かれたりしました。 こっちは玉介師匠も知ってるんだし、奴さんくらい・・・なんて思っても、知らないふりをします。 そうすると師匠は「若いもんはだめだねぇ」とかなんとか言って、先に進みます。 お年寄は大切にしないといけませんからね。
その点、笑いが起きないような若手のコントなんかの場合は、例えば、ライターを持たされて、「えいっ、と声をかけたら・・・解ってますね?」って言われても、「はい」と言いながら、火をつけなかったりしました。 そうするとプロが慌てます。 その慌てぶりに会場が笑うんで、兎に角、芸で笑いを取ったんではないけど、一応盛り上がるから、そんなこともしました(嫌な客です)。
最近はホントに寄席に行かなくなりました。 来月は住吉踊りなんだけどなぁ、今の助六さんじゃ・・・。
(註)寄席は10日ずつの興行が基本ですので、31日の時は一日余る計算になります。 そういう日に特別興行をしたりします。 「三遊亭○○一門会」とか「○○ひとり会」とか。 東京は落語家さんが主流ですので、漫才・コントなどの「色もん」だけの日とかも。 歌舞伎座で舞踊の会をするようなものです。
7月26日(木)
え〜、またまた『ジャイアント・ロボ』で恐縮です(でも、これを始めた頃って、ひとつのネタを引っ張っているってことやってたから)。
ギロチン帝王率いる「BF団」が国立競技場(だったと思いますが)の6万人の観客を一瞬にして消し去ったというプリンセス・テンコーにも出来ない芸当をしました。
地球侵略を目的としながらも、名前とは裏腹のどこか優しい感じのするギロチン帝王が、ユニコーンのモニターに現れ、「どうだ凄いだろう」みたいなことを言った後の話です。
話の中心になる何とか青年(大作少年とコンビになってます)が「キャップ、奴らは6万人を魚の餌食になってもいいのか、って言ってましたね。 海に関係があるのかもしれません」って言うんです。 ギロチン帝王はこんなに解りやすいヒントを出しました。 それなのにキャップは「それがどうした」って聞き返したんです。 頼むよ、キャップ〜って感じです。
でも、ギロチン帝王は自分がヒントを出したって思ってませんでした。 だってキャップの頼りない発言が出た後、場面はギロチン帝王がいる基地に移るんですが、こんなことを言いました。
「海底深く掘り下げた穴の中に6万人の人質を隠してあろうとは、お釈迦様でも判るめぇ」 ・・・あんた、宇宙人だって言ったじゃないか! 芝居好きの宇宙人かい!
で、結局、BF団にいる男の幼い弟が、6万人の中にいるということから裏切ったために隠し場所がバレて一見落着っていう、時代劇みたいなことになるんですけど。
7月25日(水)
え〜、また『ジャイアント・ロボ』ですけど、「ユニコーン」というのが『ウルトラマン』で言うところの「科学特捜隊」でして、いいもんです。 悪い方は「BF団」と言います。 何の略だか解りません。 その首領が「ギロチン帝王」と言うのですから、な〜んだっていう類でしょう。
放送コードが喧しくなった昨今、如何に偉い人と言えども、当時は許された発言がカットされてしまうというケースがあります。 『ウルトラセブン』のキリヤマ隊長が「キチ○イ」を連呼するところがあって、そこのところだけ何言ってんだか解らなくなっているというのは、マニアでなくとも有名なエピソードだそうです。
それは、時代による社会通念の違いということで片付けられてしまっていいのでしょうが、この『ジャイアント・ロボ』は、どうもそうはいかないと思います。 何とか少年が具体的にロボに指示したわけではないのですが、怪獣を仕留めるために石油コンビナートに投げて爆死させました。 それを見た何とかいうユニコーンの日本支部だか東京支部だかの隊長が「(怪獣にやられそうになっていたので)あぁ、危ないところだった」ってホッとするんです。 こういう人間が隊長っていうのはとってもとっても危険です。
番組のおしまいに、やたらと声に力を込めたナレーションが入るんです。 「頑張れ! 大作少年(あ、そうそう、そういう名前でした) 頑張れ! ジャイアント・ロボ 地球に平和の来る日まで!!」って。
まぁね、60年末の作品なので、学生運動等で荒れていた部分もあるんでしょうけど、BF団という地球侵略者があろうがなかろうがって取れなくもない言い方には、引っかかりますね。 でも、あんな発言を平気でするような隊長がいるという設定ですから、仕方がないんでしょうね。
7月24日(火)
またまたCSの話題で恐縮ですが、『ジャイアント・ロボ』というのをやってます。 子供の頃、夏休みとかになると再放送(再々放送?)していて、何回か観た事がありましたので、通して観るとどんなのかと思って観てます。 同様に『仮面の忍者・赤影』もやってますが、共に隔週で4話づつやるのでこなすのが大変なんです(誰にも頼まれてないのは百も承知ですけど)。
ま、早い話『鉄人28号』と何ら設定が変わらないんで、笑っちゃいました。
『鉄人28号』では何とか少年が両手て持つくらいのリモコンで操作してましたが、『ジャイアント・ロボ』の何とか少年は、それが進化して腕時計式になっていまして、『ウルトラセブン』の同様のテレビ電話(最近携帯で実用化に向ってます)の如く、「飛べ! ジャイアント・ロボ」とか言って指示を出します。
でも、やられそうな時は「ジャイアント・ロボ 頑張れ!」って言うんですよ。 もっと具体的に言ってくんないと、ロボもやりにくいんじゃないでしょうか。
それから人差し指から順にミサイルが出るんですけど、人差し指と中指は、すんなりとカチャ、カチャって出るんですけど、中指と薬指の間が空くんですよね、カチャ、カチャ、ン、カチャ、カチャって。 あれNGじゃないんですかねぇ。 ずっと使い回しているんで可笑しいです。
本当に色々な所で大笑いなんですけど(あんまり言うと特撮マニアには怒られそうですが)、例えば「忍術怪獣 ドロゴン」なんていうそのまんまのネーミングとかありました。 ギャグマンガのノリですね。
その後『超人バロムワン』という特撮ヒーローものがありましたが、そこの悪の首領が「ゾルゲ」と言いまして、手下の怪人が「何とかゲルゲ」っていう統一したネーミングでした。 オコゼの怪人なら「オコゼルゲ」とか。 だんだんネタが無くなってきたのでしょうか、後半(だったはず)には、手そのままが体で、手首から足が出ているという「テゲルゲ(全部カタカナか?)」なんていう苦しいのもあったと記憶してます(デザインは斬新だったんですけど、岡本太郎氏でしたっけ?)。
いつもながカックンと脱線しましたが、という訳で『ジャイアント・ロボ』にハマってます。 何話目からこまっちゃくれた何十ケ国語を話せるという女の子が登場してきましたが、彼女のクリっとした黒い部分ばかりの目とま〜るい顔とデコと、どこかで見たようなと思いましたら、
空飛小助でした。
昨日の市場で1968年の『なかよし』の表紙になってましたから、その手の少女モデル出身なのでしょうか。 そして今は・・・? 40歳を越しているくらいでしょうけど。
7月23日(月)
いやぁ、暑い暑い。 多分判る人は少ないでしょうけど、黒澤作品『野良犬』の千秋実さんの気分です(註1)。
松井選手がオールスター通算300号メモリアル・アーチを松坂投手から放ちました。 力と力のぶつかり合いは面白いですね。 通算100号が世界のホームラン王の王貞治さんで、200号が落合さんということだそうですので、そう言う人がちゃんとなるもんなんですね。
それにしても西武のガブレラ選手は凄すぎます。 「浪花の何とか(「モーツアルト」ではないのは確かです・・・註2)」って言われているミスター・フルスイングの中村選手もいいキャラしてますし、パ・リーグの方が良い選手が多いですね。
で、肝心のあの方ですが、セ・リーグ側のブルペンで出番直前の投手にインタビューしてましたが、あんまり相手にされてませんでした(パ・リーグ側の人はもっとでしたが)。
そんなことより、今朝はちゃんとレギュラー仕事をされてました。 かなりお疲れのご様子でした。
(註1)刑事が仕事場へ聞きこみに来た時に、気だるそうな顔をしながら現れ、扇風機を顔に当てながら答えていたシーンのこと。
(註2)キダ・タローですから。
7月22日(日)
最近すっかり大リーグにもってかれっぱなしの日本球界でも、オールスターが始まりました。
「夢」だとか「お祭り」だとかいうことから、また「大リーグ熱」から、「何で三試合もやるねん」みたいなことが叫ばれてます。
それは狭い日本という北から南へと大移動しても時差も何もない国という物理的な話があってことでしょう(選挙の場合と同じ)。
あと、「都市→地方」といった図式の上で「戦後」を引き摺っているんではないかと思います。 つまり、テレビそんなに普及していなかった頃、高度成長期以前の日本にあった、「オラさ村にも東京から呼んでみっぺぇや」みたいなものと「東京もんのスゲーとこ見せたる」みたいなもの、『カルメン故郷に帰る(註)』みたいなもんですね。 だってコミッショナーとか戦前の人だったりするじゃないですか、日本シリーズのMVPの賞品(賞金じゃなくて)に豚(牛じゃなったはず)とかでた頃で感覚的には止まっているんですよ。
それもこれもさっきも言ったように狭い国だからできる話なので、別にいいんじゃないと思うんですけどね。 「巨人・阪神OB戦」みたいにおじいちゃんが多く出るんだったら一試合でも仕方がないんですけど、現役の人たちなんだから。
それにしてもパ・リーグのクリーンアップは凄いメンツでした。 あれじゃピッチャーは怖いだろうと思います。
今日は横浜であるんだそうですが、TBSなんですよねぇ。 あの方をはじめ数人のアナウンサーが浴衣でインタビューするんだそうです(朝10時からの同局の番組で言ってました)。 あの方は、その番組にいらっしゃいましたので、今日は12時間近くも労働させられて、明日の朝6時にはレギュラーに出るんですから、大変でしょう。
今から球場に行って、正規ルートではない入手方法でチケットをゲットしたところで、本人はダッグアウト近くの特設スタジオなんかにいらっしゃるんでしょうから、お会いできませんでしょう。 だから行きませんけど。
そんな事より、明日から「夏休み」とかいうことにならないことを望みます。 昨日は家に居たのに『チューボー・・・』を忘れたし・・・。
それよりも、今日の取材を契機に「野球選手と熱愛」とかにならないことを切に望みます。 あの局はイチローの例があるんで・・・。
(註)昭和26年公開の本邦初の総天然色(オールカラー)映画。 監督は木下恵介、主役は高峰秀子(昔のJRのCM「フルムーン」の人ではありません。 あれは、高峰三枝子)。 東京に出ていった娘が芸術家となって故郷に錦を飾りに戻ってくるというので、村中あげて大歓迎しようとしたら、そこに現れたのがド派手な格好をした芸名を「リリー・カルメン」というストリッパーで、村中はてんやわんやっていう話。
7月20日(金)
「カフェうどん」なるものが流行っているそうです。 巷に溢れているカフェでうどんを置くようになったっていうんじゃなくて、「パスタのようにオシャレにうどんを食べませう!」っていうことみたいです。 当然、若者の行くようなオシャレな街にしかないみたいで、私の住んでいる深川の方になんかありゃしません。
パスタの世界でも、ミートソースに納豆が入っているものがあるみたいで、カフェうどんですと「冷やしたぬき」とかじゃなくて、マヨネーズたっぷりの「サラダうどん」なんか人気みたいです。 そういった世紀末的な匂いがプンプンするものが新世紀になっている今でも受けているっていうは不思議です。
でもどんなに気取っても「うどん」っていう響きを何とかしないとねぇ。 「スパゲティー」という子供っぽい響きを「パスタ」と定着させたように。
そう言えば、昔々、江戸時代に「黄表紙」なる絵本がありました。 絵本と申しましても、どこかでご覧になったかと思いますが、子供の読む「のりもの」とか「どうぶつえん」とか言うものではありませんで、大人の読んだ・・・と申しましても、エッチなものとお考えにならないで下さい。 ページいっぱいに大きな絵が描いてあって、その廻りに読みにくいニョロニョロした字が隙間なくあるのをご存知ではないですか? 「余白の美」などはじめから存在しないってやつでございます。 ま、全体のレイアウトっていう感覚がなかったんですから仕方がないんですけど。
そこに、あれ、何だったっけ? ・・・題名忘れましたが、江戸(地名のです、ピリオドではなく)に歴史のある「蕎麦」が、上方からやってきた「うどん」によって、それまで独占だったものが危うくなってきたので、何とかして江戸の町から「うどん」を追い出し、以前のように天下泰平にするために立ち上がるという話がありました。 作者は山東京傳でしょう、こんなこと考えるのは、確か。
「うどん」と戦うために「七味」がそれぞれ武装している絵があったりしました(人間に見立てるんです、頭はそれぞれの薬味のままで、着物に丸に頭文字が平仮名で書いてあるので、誰なんだかが判るようになってます。 ビートたけしさんが「牛田もう」名のって牛のかぶりものしているようなものですね)。
途中、天皇に勅旨をもらうんですけど、天皇は「そうめん」でした。 落語になるような話なんですけど、なってないのかなぁ・・・。
7月19日(木)
11日に『夜のヒットスタジオ』が急に1980年になってしまったと書いたんですけど、一週間たったら82年になってしまいました(81年は全部放送不可なのかー!)。
ぶりっ子・聖子ちゃんは『小麦色のマーメード』になってましたし、横浜銀蝿は本家をかっ飛ばして弟分のグレース(だったかな? ま、そんなの)とかいうのになってるし(島何とかさんとか、岩井何とかさんとかではない)、石川さゆりさんは結婚してしまってるし(そんなのははじめて知ったんですけど)、松本伊代さんは相変わらず二人のお姉チャン引きつれていたし(あ、これはそのまんまです)、河合奈保子さんは「あれ? 大人っぽくなったなぁ?」って思ったら、あのとんでもない曲『けんかをやめて』なんか歌っちゃうし・・・。
そんな中で、拾い物って言うと(本人には失礼ですが)、伊藤さやかさんでした。 あの『金八先生』に出ていた「伊藤つかさ」ではないです。 テレビ実写版『陽あたり良好』の何とかいうヒロインやってた人です。 すっかり記憶から消えてましたが、ライブハウスに聴きに行ったことを思い出し、今更ながら恥ずかしくなりました。 何で行く気になったのかはよく覚えてませんが、多分、テレビ観てたからでしょうか。 『天使と悪魔 ナンパされたい編』という曲でしたが、覚えてましたから、シングル買ったんでしょう・・・。 作詞が「HEART BOX」となってましたが、『ウエディング・ベル』の「SUGAR」の曲の詩の多くをこのユニットが担当してましたが、誰なのでしょう。 「SUGAR」の三人のことなのでしょうか?
81年が丁度20年前ですから、何とかこの年のものを聴きたいというか観たいものです。 この年の3月にYMOが『BGM』というそれまでの「ピコピコ・サウンド」のミーハー・ファンを切り捨てたアルバムを出し、6月にはメンバーのドラマー高橋幸宏さんの3枚目のソロアルバム『ロマン神経症』が出て、20年前の私はスゲー、スゲーって叫んでいたんですから。 当時は最先端の音楽を聴いていたんです。
当時、ソニーの20何万したステレオ(昔は高かったですよねぇ、ミニコンポもない時代でしたし、って私が払ったんじゃないんですけど)で、はじめて針を落とした瞬間のトキメキったらなかったですね。 中学3年(かな?)になってましたから、それなりに「音」に対する興味もあったんで、YMOとしてもそうですし、ソロでも次から次へと「新しいも音」になっていくのがよかったんですね。
もっと大人でしたらどうだったか判りませんが、多感な時期にテクノという音楽の洗礼を受けたんですから、プレスリーやビートルズ世代と同じように幸せだったんだと思います。
ただ、ボーカル曲が多くなったのと、多重録音が凄くなってきたので、音楽の授業の前でちょこっとピアノで弾くってことが出来なくなったことが残念でなりませんでした(『RYDEEN』とか弾くと「古い」って感じでしたし)。
7月18日(水)
東京駅八重洲口駅前に太い通りがあります。 そこを駅を背にして右手(つまり、銀座方面)を見ますと「八重洲ブックセンター」があります。 その一本先の路地で、ブックセンターの延長線上に「ヒカリカメラ」という知る人ぞ知る中古カメラ屋さんがありました。 そう、過去形になってしまいました。 閉店してしまったのです。
百貨店などでも中古カメラの催しものをやると、いまだにいい売上があるといわれていますが、そうした背景があってかどうかは判りませんが、兎に角閉店してしまいました。
お店は角にありましたので、片側のショーウインドウには一眼レフやレンズがあって、もう片側には8ミリカメラや映写機などがありました。
学生の頃にたまにウインドウを見ては、「ZC−1000(8ミリ小僧の憧れのもの)」が出ていると指を加えた淡い想い出もありました。
7月17日(火)
え〜、またですが、まずこちらをお読みくださいませ。 ⇒
GO!
二葉亭の場合は言い放った感じで許されるんですが、大前田青果の場合は「お前ら」と見下した感があるんで今一つではあったんです。 ですので、はじめはフルネームで使ってたんですけど、そういう感じがするのと、長くて堅苦しいんで、今では「青果」だけを使っている今日この頃でございます。
昭和30年代半ばになると、東映の大部屋俳優さんで「大東 良(多分、だいとう・りょう)」という人がいましたが、こういうのは「世志凡太(漢字は合ってるかな?)」まではいかないけど、「谷啓」に勝るものはないし、ちょっと好みからははずれてしまいます。
昨日、古い番付を整理してましたら、中に映画館のプログラムが入ってました。 エノケン一座の実演でしたが、その中に「大方宗太郎」という人がいました。 もっても気に入りました。 このトボケタ感じがいいです。 どんな人で、この後はどうなっていったのかまったく判りませんが、こういう「文」を名前にしたものを考えたいです。 「GO!GO!! 大前田青果 改名大作戦!!」 この夏のテーマが決まりました。
7月16日(月)
・・・・。 何にも書くことが浮かばない・・・。 こうなればと、一年前のページを見てみました。
え〜っと、何々。 『はいからはくち』について書いてますねぇ。 こうして過去のを読み返してみると、書いたことすりゃ忘れていることが結構ありますね。 「♪忘れちゃ嫌よ 忘れないでねぇ〜」っていう唄がありましたが、最近は三歩歩いたら忘れてしまいますから・・・。 たまに過去へGO!とかやってますが、「確かあったはず・・・」とキーワード検索してやっているんで、ちゃんと覚えてなんかいませんので、念の為。
で、前後を読んでみました。 すると自分で書いておきながら、何の事だか解らないのがありました。
7月10日なんですが、何の事なのでしょう? 「○印」って。 どなたか教えてください(情けなし・・・。)
7月15日(日)
日本のどこに行っても黒山の人だかりで、まったくその人気たるや、戦後に昭和天皇が全国を廻った時みたいです(ホントかなぁ)。
自殺未遂事件が起こったのがわかったら、見に行ってたのにぃ! お店にテレビがないのが残念です。
でも、テレビなんかあったら「昼ドラ」から夕方の時代劇とか(今もやってるのかな?)ず〜っと観ちゃうことになるでしょう。 何せひとりっ子でテレビっ子でしたから(オール阪神さんは「ひとりっ子でチビッ子」)。
そうか、テレビデオでも買えば、溜まっている映画が観れるぞ、マジで考えようかなぁ
7月13日(金)
え〜、まずこちらをお読みくださいませ。 ⇒
GO!
お恥ずかしい話で恐縮でございますが、そういうことがあったんです。 で、それ以降、番組は欠かさず観ておりますが、特にデータを取っている訳でもないし、かと言って意識して観ている訳でもないので、この数ヶ月の間がどうだったのか、自分でも感触がないんですが、今週はパーフェクトでしたので、久しぶりに驚いちゃいました。
で、実際問題どうなんでしょうねぇ。 こういう4択問題が5日間連続で同じっていうのは。 確立で言えば「1024分の1(でいいんですよね、確か)」ってことなんですが、これが心理テストだからねぇ。 深層心理で海より深く結ばれているってこと? キャー、キャー! ちょっと来週もデータとってみようっと。
7月12日(木)
大リーグのオールスターで「イチロー」が「大魔神」とともに活躍しましたから、そりゃ飲めや歌えやの大騒ぎですが、四月以降、こう「イチロー、イチロー」言われていると、全国にいる「いちろう」さんはどういう風に感じるのでしょうか。 あっちはカタカナだし、それに天才だから何とも感じないのでしょうか。
例えば元タカラヅカの「いちろ・・・何とかさん(漢字がわかりませんが、ちょっと前、東宝系の映画館で予告編と一緒に流れてたCMに出てた人)」とか、財津一郎さんとかはどうでしょうねぇ。 「紛らわしいから、やめてちょーだいッ!」って言ってはいないのでしょうか。
ま、有島一郎さんとか並木一路さんとかはお亡くなりになっていますので関係無いのでしょうけど。 あと誰がいたかな・・・。
7月11日(水)
CSの『夜のヒットスタジオ』も漸く1980年になりました。
不規則ではありましたが大体その月の分を一本という風にして、週二本(二ヶ月分ということ)ペースでやってました。 先週が4月分まででしたので、今週は6月にYMOが初登場した時の週でもやればと期待しましたけど、一気に8月に飛んでしまいました(それも最終週分)。 YMOの映像は昔LDで出ましたが、よくある諸般の事情ということで演奏部分のみでした。 私の記憶によると、司会者に特別ゲスト的に紹介されたはいいが、番組で有名な奥の階段のセットから無言で出てきて、止めるとを無視してカメラの方に向かってきてそのままフレームアウトしてしまったはずなので、それを確認したかったんですけど、こちらも諸般の事情なのでしょうね。 残念でした。
ということで、ゲストにとうとう河合奈保子さんが登場しました。 河合坊茶のように名前に引っ掛けているのかどうかは知りませんが、とっても可愛いかったです。 私より2〜3歳上だったような記憶がありますから、あの当時16〜17歳だったのでしょうけど、今の娘より肌が壊れてないでしたね。 そう言えば、中学の時に逗子の方までコンサートを観に行ったことがありました。 番組ではセカンドだったかサードだったか忘れましたが『ヤングボーイ』という「秀樹の妹」としてはちょっと暗めな曲でしたが。
あとは八神純子さんが『パープル・タウン』を歌ってましたが、イントロのシンセが当時の硬い音で懐かしかったです。 布施明さんがオリビア・ハッセーさんと結婚するって言ってましたが、この頃なんですね、当時も今も「ふ〜ん」で終わってしまいますが。
こうして観ると、79年と80年でかなり垢抜け度が違います。 もう2〜3年すると歌が下手なアイドルたちがヒラヒラとしたものを着るようになってくるんですが。 そうなるまでは楽しみです。
7月10日(火)
歌舞伎俳優の十七代目市村羽左衛門さんが亡くなられました。
年明け草々の九代目澤村宗十郎さん、三月末の六代目中村歌右衛門さんと、今年は大物が相次いで亡くなってしまいました。
大きな名前が同じ年に消えることは、近代ではに明治三十六年の九代目市川團十郎と五代目尾上菊五郎、昭和十五年の五代目中村歌右衛門と二代目市川左團次、昭和二十四年の七代目松本幸四郎と六代目尾上菊五郎とありました。
その都度世代交代して、歌舞伎は雑草のように生き延びてきました。 来年から松緑、海老蔵、勘三郎など大名跡がどんどん復活していきますが、過渡期にいる者にとっては、過去の記憶をなかなか捨て去ることはできないものです。 どのようになっていくのでしょうか。
7月 9日(月)
世間的にはちっともそうでないんですけど、自分の中で「幻」となっているものがあります。 神保町にある自家製パン屋さんの「りんごパン」がそれなんですけど、そこはお店自体のスペースの問題もあるのかもしれませんが、種類を豊富にしているために量産してないみたいです(かどうかは不明)。 テレビでも取り上げられたことのある有名なところです。
そういうこととして、いつもタイミングが悪くてお目にかかったことがないんです。 よって「幻」。 神保町にいる時間がもっと長ければいいんでしょうけど。
で、どうしてそこまでこだわるのかと言いますと、ショーケースに「りんごパン シャレた味」って書いているんですから、気になるでしょ? ほかのものには何にもキャッチが付いてないんですから余計です。
昔のメロンパンみたいに味が違うっていうのではないのは想像つきます。 洋梨のようにりんごを半分か、スライスしたものがドンって入っているんでしょうし、それに何か味付けているのかもしれませんが、そのどういったところが「シャレ」ているのか!
で、今日とうとう出会いました。 二日遅れの七夕さんです(明日だと便りを乗せて行っちゃいますが・・・ ←本文とまったく関係ありません)。
パンは半円のコッペで(よくコロッケとか揚げ物を挟んだものに使用するようなもの)、一センチくらいにスライスしたりんごが入っていて、それにすまなそうにクリームがチョンと乗ってました、それでおしまいでした。 シャレで売ってるんでしょうか。
7月 8日(日)
「期待」と「満足」の話です。 ある人の話ですが「期待感が高過ぎると、いくらこちら側がいいものを提供しても満足してもらえない、だから期待しないでね」と舞台の製作発表記者会見で話したそうです。
それはもっともなことですが、「頭では解っているつもりでも・・・」というのがあって、それがファン心理の恐ろしさでもあるのでしょう。
映像ではないエンターテイメントにおいて、それを表現するものは「生身の人間」です。 サーカスや見世物芸など、普段大して考えたことは無いだろうと思える人間の体力的な限界を目の前で超越するという意外性が驚きでもあり、感動でもありってことでしょう(目の前で火を吹かれてごらんなさい)。
ま、全部が全部あなたの知らない世界的な超常現象と紙一重ちゅーものでなければ、エンターテイメントとは言えないなんてことはないのは承知です。
でも跳躍ひとつとっても人より高く飛べる人がいれば、そちらを「見てみたくなる」のは人情で、だからオリンピックなど盛り上がるんだし、『筋肉番付』のような番組も出来てくるんでしょうし(個人的には『ビックリ日本新記録』みたいなものの方が好きだけど)。
で、話を舞台に戻しますが、そう言った「前提(私はそう思う)」の上に、つくり手の「意図」「テーマ」「主張」・・・まぁ何でもいいですが、そういったメッセージみたいなものが加味されて表現されると感動を呼びます。
旅を続ける「○○一座」という幟の立っている大衆演劇ですと、座長である○○さんが、歌って踊って芝居して始めっから仕舞いまで出づっぱりでいて百何十パーセントのサービスをするから、絶大な支持を受けている訳です(この際量は置いときますけど)。
しかし、そうしてフル活動できるにも体が資本ですから、年齢的・体力的にいづれ限界が来ます。 そこで今までと違う路線に変更するか、衰えても今まで通りに貫くか、はたまた潔く引退するか。 当然、引退以外は今流行りの「痛み」が伴う「賭け」でしょう。
では、ファン心理としてはどうなのでしょうか。 全盛期を共に歩んだだけあって、老いた姿は見たくないから、引退して記憶の中に収めておきたいという人もいるでしょう。 そういう意味で本家は続けていてもファンの方で切り離してしまうケースもあるでしょう。
従来通りのパターンで異例な演劇は「戦後歌舞伎」でしょう。 病気で倒れた老役者が久しぶりに出るというだけで、「早めに観ておかなきゃ」と初日から駈けつけます。 舞台に上がるだけでもやっとの役者を「そこにいる」というだけで「感動」を呼ぶ、不思議な演劇とその客層です。 その逆もあって三歳くらいの(最近はそれ以下の場合もありますが)「初舞台披露」ということで、まだこの先どうなるかも判らない子供が「よ・ろ・し・く お・ね・が・い い・た・し・まちゅ」って言っただけで、場内大拍手という他からみれば珍なる現象が起きます。
そのジャンルで人気、観客動員など申し分の無いスターの地位に長い間君臨し続けて、しかもそこに甘んじることがなく、ずっと抽象的ではありますが、あらゆる意味で挑戦し続けた役者兼プロデューサーである人がいます。
その人の舞台は、常に始めて観る人までを対象とした作りになってまして、20世紀の終わる昨年、長年の活動のひとつの節目を迎えました。 さてそれならば21世紀はどうなっていくのかと期待しつつ、いや私個人としてはプロデューサー思考の強い人故に、もう役者としてどうこうと「本人は思っていないはず」と勝手に考えてますから、期待はしないどこうと思いながら彼の舞台を拝見いたしました。
芝居としてはよくまとまってますので、とっても良かったんです。 しかも会場は割れんばかりの大喝采で、プロデューサーとしては大成功です。 無事今世紀もスタートできました、というところでしょう。
でも、これは私だけなのかもしれませんが、そこには役者としての「志」をどこかに置いてきてしまったかのような形をなぞるだけのプロデューサーに雇われた役者さんがいた、という感じがしてしまいました。 決して「やる気が無い」とかいうことではありません。 ある程度は予測してましたが、「そこまで割り切れるのか」と同一人物であるが故に複雑な気持ちでした。
う〜ん、こういうことなのかもしれません(勝手に思うだけですが)。 昔、自分の演劇的スタイルを完成させようと志した役者がいました。 彼は自分でプロデュ−スして奮闘してきました。 しばらくしてファンがつくようになって、より自己の演劇的活動を進めてきました。 そのうち、スタイルが完成されましたが、それをまた違った形で表現することを始め、それも評価されました。 ところが、役者としての体力が年齢と共に下降していく時期に入っていき、しばらくそうした物理的な問題と自ら格闘してきました。 ある作品で、それを解決することが出来ました。 それは役者とプロデュ−サーの分離です。 プロデュ−サーが自分自身を一人の役者として扱う、それも主役としてではなく、これはなかなかできないことではないでしょうか。 そしてその作品は興行的に大成功しました。 そこで単純に考えると、役者兼プロデューサーであるならば、役者の部分がそれをどうして許すことができるのだろうということです。 しかし、そこが勘違いであって、役者兼プロデューサーと思っていた人は、実はプロデューサー兼役者であったのです。 これで作品が興行的に失敗したのであれば、はやり役者の部分を真っ先に考えてこれからも物理的な問題と格闘しながら作品作りをしていかなければならないのでしょうが、プロデューサーとして今までの作品作りのノウハウに間違いはなかったと改めて自信を持つことになりはしないでしょうか。 つまり彼が若い頃に自らを主役にして奮闘してきたことを、また復活できるのです。 それも場合によっては自分自身を出演させないでできる、正にスタイルの確立です。 これはこのジャンルにおいて特筆すべき事柄なのではないでしょうか。
長々となりましたけど、自分自身で整理がついているようでそうでないようで、それ以前に指摘があっているのか否かっていう問題もありますけど、ま、ひとりごとですから。
7月 6日(金)
銀座から新橋にかけてとある抗争事件が起こっていたり、同じアパートに住む人に殺され、しかも当人はテレビのインタビューに平然と出ていたなんていう物騒な世の中に、正に明日の「七夕」のような純愛話(?)が起こりました。
歌舞伎の三代目市川猿之助さんと日本舞踊家で女優の藤間紫さんとの半世紀余りのカップル誕生です。 週刊誌なんかは「超熟年ケジメ婚」なんてタイトルをつけるのかもしれませんが、この2人は今に始まったことではないし、複雑な過去は個人の問題ですので触れません。
彼のつくった「スーパー歌舞伎」で「浪漫の病」をテーマのひとつとした『オグリ』という作品がありますが、結局あれでしょうか。
しかし、彼は人のやらないことをしますねぇ。 立派、立派! 彼のコメントにもありましたが「お互いどちらかが先に逝った場合のことを考えて」ということですが、普通は平均寿命以上の歳の差があるのだから、紫さんの方が・・・なんって思うのでしょうが、彼の場合は何ともいえないですのでねぇ。 ああいう風に休まず突っ走ってきた人ですし。
ま、兎に角、熟年離婚が流行っている中で、少しでも「夢」を与えてくれたのではないでしょうか。 彼らしい感じがします。
テンプターズの『純愛』ですと 「♪腕に傷をつけて 腕と腕を重ね 若い愛の血潮 分かち合った恋は 誰も誰も壊せはしない」なんて歌詞がありますが、年齢的に血は濁っている・・・あ、これは失言です。
7月 5日(木)
先日、『NHKアーカイヴズ』で戦艦陸奥の陸揚げと特攻隊の二本立てをやってました。 いつだったか大和が沈んでいる所にカメラを持っていって「菊の紋章をとらえた〜!」とかやってましたが、それよりも四半世紀くらい前に、こんな大事業をやっていたんですね。
結果、そのほとんどが鉄クズになったっていうのは、あの当時だったからなのかも知れません。 今なら「何でもかんでも資料として残せ!」って戦後生まれの人たちが言いそうです。
もう一本の方は「特攻の生き残り」というレッテルを貼られた人たちの戦後を語ってました。 戦争中は「息子をよろしく」と言った人が戦後は殺人者呼ばわりされるとう話や、故郷に戻っても後ろ指刺され続け、その後仲間の供養にと基地のあった近くに住み、今はキリスト教によって救われた気持ちになっている人の話などありました。
また「お前らは生きろ」と言って出撃させなかった上官の話もあったし、出撃命令をもらった時の気持ちを二人に聞いても「喜んで散ってきます」みたいなものではなかったという証言もありました。
戦後30年くらいですと様々な立場の意見が取材できるので、多方面から証言を取ることができました。 現に特攻基地があったある町で記念式をやるにあたって、当時みんなの世話を焼いた食堂のおばさんが経営している旅館で当事者とその家族を集めた同窓会があったんですが、キリスト教の人はそれには参加しませんでしたし、また、参加した一人は自分の鉢巻などをそのおばさんにもらってもらい「過去との決別」をした人もいました。
初期の『金八先生』で特攻服を着た応援団(だったかな)の生徒を校長先生(今は『渡る世間は・・・』でお馴染みの人)が当事者の、気持ちを考えろと怒った話がありました。
もうその時点で「神風特別攻撃隊」は「将来のある若人を、自分の意思に関係なく、戦争という出来事とそれを取り巻く環境が、勝手に奪ったもの」で、彼らは皆「悲しんで死んでいった」ということになってしまっているんですねぇ。 ドラマなどで戦後直ぐのヤミ市で『東京ブギウギ』が流れていたっていうのと同じように、太平洋戦争=『同期の桜』ちゅうことではないわけです。 ま、仕方がないんでしょうけど。
7月 4日(水)
CSのお陰でビデオ化されない古い日本映画が観れるようになって、ありがたいんですが(ありがたや節の映画もありました)、子供の時に観たテレビ番組もやってくれてます。
最近始まった『がんばれ レッドビッキーズ』などは懐かしいです。 それぞれの子供達が「いたいた〜」って感じで。 特に「そうそう! あったあった!」って思わせてくれたのが、番組中に沢山入る主演の黒澤監督の息子婦人の喜怒哀楽を表現したイラストです(原作が石森さんだからでしょうか、『仮面ライダー』などでCMになる時に出た、ああいうやつ)。
当時も沢山入っていた印象がありましたが、まったくその通りで、下手すりゃ一回放送に十回はあるかもしれません。 でもこれは便利な手法で、イラストを出すことによって今のエピソードをどんな状況でも終わらせてしまうことができ、次のエピソードに容易に行けるからです。 黒澤の『用心棒』で話が煮詰まった時にすぐワイプするのと同じです(当時、彼から指示があるわけないし)。 こういうのは「やったもん勝ち」なんでねぇ。
また、こんなの残ってたんだぁっていうモノクロの連続物もやってます。 『あいつと私』という、昔、日活で石原裕次郎さん主演の学園ものがありましたが、そのテレビ版です。 映画の方は、個人的に顔がタイプの芦川いづみさんでしたが、テレビ版は元SPEEDの何とかさんに似ている松原智恵子さんです。
映画版は主題歌を裕次郎さんが明朗に歌ってました。 「♪あいつはあいつ 俺は俺 あいつと俺は友達だ やぁ!」 と人生幸朗師匠に「当たり前じゃ! ドアホ!!」って突っ込まれそうな出だしですが、これがどこかのカラオケに入ってまして、知り合いが「「♪あいつはあいつ 俺じゃない〜」って歌い、その先が歌えなかったことがありました。 「何じゃ、それ! ボケ! カス!! ハナクソ〜! ホンマにぃ〜」とは突っ込みませんでしたが・・・。
そう言えば、昔、さだまさしさんの『印象派』というアルバムに『検察側の証人』という曲がありました。 「♪あいつを 捨てた女は 今ごろ別の 男の部屋で・・・」という歌詞で、二番は男女が反対になります。
これを当時大ファンだった男がいまして(男っちゅーのがいいですね)、そいつのそばで 「♪あいつを 捨てた女は 今ごろ別の 女の部屋で」で歌を切って「レズになりました〜!」っと突っ込んでからかったことをがありましたっけ(感覚的には『演歌チャンチャカチャン』の感じです)。 当然二番は「ホモになりました〜!」 可愛いもんです OR 親父ギャグ予備軍 どちらでしょう・・・。
7月 3日(火)
現代写真週刊誌の草分け(現代ってしたのは『アサヒグラフ』とかあったので)の「フォーカス」が休刊というか実質廃刊するとこのとです。 ライバル誌「F」は笑いが止まらないことでしょう。
一時は「フォーカスされる」という言葉まで出来たくらいですから、その勢いはよく覚えてます。 コンビニで立ち読みする習慣がないので、ここ数年は銀行か床屋あたりで見る程度でしたから、部数が激減していたとは全然知りませんでした。
ですので、ライバル誌との個性の違いは判りません。 が、もっと軟派な似たような雑誌が残るというのは、何となくわかりますが、あちらが残ってこちらがダメっていうのは、一見同じように見えても中身が全然違うんでしょうね。 個人的には謎です。
謎と言えば、鞍馬天狗で有名なアラカンこと嵐寛寿郎の、もうひとつのシリーズものの『右門捕物帖・片目の狼』という昭和26年の作品に「高瀬みのる」という名前が出ているんです。
映画のだいたい半分近くで、舞台となる大きな・・・あれ何だろう、宿屋かなぁ・・・大広間みたいなところで、女の人が「たかせさ〜ん」って言うと、あの扮装をした、でもいかにも若くて別人の人が出てきて「あ〜のね」って言うんですよ。 そして片目の浪人に扮したアラカンに顔をチョンと殴られると「あ〜のね、オッサン・・・」って言ってバタンって倒れておしまい、時間にして10秒ちょっと。
あれ誰なんでしょう? 曾我廼家五郎みたいに二代目を名乗った人がいたんでしょうか? 息子がいて継いだとか(大辻司郎⇒伺郎みたいに)。 それとも監督が中川信夫だから、後先考えずに適当にやっただけのことなのでしょうか?
7月 2日(月)
「あのねのオッサン」って言っても、何じゃそりゃってなもんでしょう。 「あのねのね」でも「♪ヤンケ〜ヤンケ〜セヤンケワレ〜」の河内のオッサンでもありません。
戦前から戦中にかけて活躍した喜劇俳優です。 風貌は娘さんそっくりな頭に、脇に毛があるだけで禿げかつら、天辺に「バカ殿」みたいなちょんまげをつけて、目の下を黒く縁取った化粧に、鼻の下に口髭・・・こんなところでしょうか。
その風貌もさることながら、「あのねオッサン、ワシャかなわんよ」という捨て台詞が大流行したために、代名詞として使われたわけです。
正確には「あ〜のねぇ オッサン、ワシャか〜なわんよ」と言うのですが、判り難いでしょうか。 「あ〜」は高いところから発声して「オッサン」まで一気に言いまして、「か〜なわん」のところは「か〜なぅわぁんよぉ」と、これも同様に一気に言いますが、「なぅわぁんよぉ」のところを市川雷蔵さん風にこもった発声をするとバッチリかもしれません。 『オッサンの・・・』という題名でレコードを何枚か出してます。 「オッサン」は普通名詞なんですけどねぇ。
ま、そんなモノマネ講座は置いときまして、以前読んだ本(何だったかは忘れましたが)に、彼はもともとは普通の役者だったと書いてありました。 確かにチャンバラもので敵役をやって鍔迫り合いしているスチールを見たことがありましたし、ほぼ全編が現存している『御誂次郎吉格子(註1)』なんかでもそうですし。 でも『國士無双』っていう映画には、既にそのほぼ完成しているキャラで出てたりしてます。 古い邦画が好きな人でしたら、山中貞雄監督の現存する三作中二本(註2)に出てますし、東宝映画ならいろんなものに出てます。 戦後になっても2〜3年は生きてました(註3)。
これは小沢昭一さんの話だったでしょうか、子供の時に國民学校で「あのねオッサン、ワシャかなわんよ」が流行りに流行ったのだそうですが 時節柄、不謹慎極まりないということで、言うことを禁止されたんだそうです。 「あのね禁止令」 凄いですよね。 私も「インベーダー・ゲーム」が流行ったのでゲームセンターへ出入りを禁止させられましたが、そんなのとはレベルが違います。 「ピンクレディーを踊ってはいけない」とか「ぶりっこ禁止令」とかありませんでしたもん。
(註1)「おあつらえ・じろきちごうし」と読みます。
伊藤大輔監督、大河内傳次郎主演、昭和6年・日活作品。
(註2)『丹下左膳余話・百万両の壷(1935)』 『河内山宗俊(1936)』 『人情紙風船(1937)』の三本のうち、先の二作に出てます。 さすがに『人情・・・』には出せません。
(註3)焼け野原の記録映像としての価値が出てきた『東京五人男(斎藤寅次郎監督・エンタツ、アチャコ、ロッパほか ←それぞれに註はつけませんのであしからず))』で、古川緑波(=ロッパ)が食べ物を分けてもらおうと訪ねた先の成金農家の親父で出てました。
またエノケンとシミキンが出た『幸運の仲間(だったかな? 「♪あの〜ね、あの〜ね」で始まる主題歌のやつ)』に、どこかの偉い議員役で出てました。 このあたりが最後なのでしょうか、それなら主題歌の歌詞が皮肉にきこえますけど、作者の意図するところでは絶対にないでしょう。
7月 1日(日)
え〜、早いものでもう七月でございます。 梅雨の中休みってぇ申しますが、こう長くっちゃ「長休み」でして、長い休みとお申しますと、真っ先に思い浮かべますのが「夏休み」でございます。 するってぇと、梅雨が夏休みをお取りあそばしてらっしゃると、まぁ自分で何を言っているんだか判らなくなりますが・・・どうも落語のマクラみたいになってしまい甚だ恐縮です。
私は関西に生まれておりましたら、歌の文句じゃありませんが、今以上、これ以上、毎日が楽しいことでしょう。 と申しますのも、落語よりかは、漫才などのいわゆる「色物」が好きでございますからして、私が御幼少のみぎりには、写真右のスミ子さんに恋焦がれていたかもしれません。
しかし、東京に生まれてしまいました関係上、「スミ」と言えば玉川スミさん、そして写真を見ても左の高瀬ぎん子さん(註1)の方に関心をもってしまいます。
そんな落語にあまり馴染みの無い私が好きな落語家と言えば・・・、
「そうだな、文楽だろ?」
「君ねぇ、今までの流れからすると、そうはならないでしょ? 判らんかなぁ」
「じゃぁ、志ん生だ、志ん生」
「違うんだなぁ」
「え? 志ん生じゃない? どうして?」
「う〜ん、CDであまり多くを聴いていないからかもしれないけどね、君、昔観た『銀座カンカン娘(註2)』の印象がねぇ・・・」
「ほう、つまり、志ん生の印象が悪くって心象を害したんでござんしょう、ってことになのかい?」
「何を詰まらないことを言ってんだよ、君」
「じゃぁ、誰だい? こないだ死んだ三木助の親父かい? 円生かい?」
「いいや、そんな上品じゃ」
「あ、渋いところで可楽かい?」
「どんどん遠くなってくるねぇ、もっと爆笑につぐ爆笑な、ね?」
「金馬かい? A藤T夫が認めなかった」
「そうそう、そっちの方向だよ、他には?」
「ほらほら、助六だったっけ、助六、おばあさんキャラで売った事もあったし、ね?」
「違うよ、ついでに言わせてもらえば関西じゃないから五九堂のおばあちゃんも知らないからね」
「そうかい、僕なんか、花川戸助六ならぬ、花川戸六助っていう売れなかったコメディアンの名刺をもってるよ」
「何だいそりゃ、ぜんぜん自慢にならないよ、もう降参だね?」
「降参も何も、どうして漫才形式になってんだい、これ?」
「ん? 僕もよく判らないんだけどね」
・・・ってあんまり長く引っ張っても何なので止めますが、痴楽なんです。 「鶴田浩二や錦之介、あれより ず〜っとイイ男」の痴楽です。 可笑でも長生きしていりゃ、わからなかったですけど、とにかく好きなんですね、落語好きにケチョンケチョンに言われようが。
そのライブCDが三枚出たんですけど、5〜6年前に出たCDブックみたいなのとダブっているんですよ、演目だけみれば。 家に帰ってそのCDブックを見たんですけど、データ的なものが何にもないので判らないんです。
それで「ラブレター」というのが「昭和33年版」と「39(だったかな?)年版」とあるので、33年っていうのは多分違うなって思って、そちらを買いました。
するってぇと、若いからかもしれませんが、「勢い」が全然違っていていいんです。 それにダブっていると思ったものも、違う時の音源だったので「ラッキー・カムカム」状態でした。
(註1)戦前に一世を風靡したコメディアン高瀬實乗の娘さんだそうです。 蛇を食べたという逸話のある父をもつっていうのは、どういう心持ちだったのでしょう。 「E・H・エリックの娘」っていうのが嫌だったくらい何だ! ぎん子さんは「あのねのオッサンの娘」なんだぞ!
(註2)大映が誇る(?)俳優出身の島耕二監督作品。 もちろん「♪あの娘 かわいや カンカン娘〜」ではじまる服部良一氏の名曲を主題歌にしたもので、高峰秀子、笠置シズ子、岸井明らが出てます。 「クライマックスでは、名人・志ん生の落語がたっぷりと聴けるという、パラマウント調を意識したソフィステケーテッドされた傑作コメディ」というのがテレビ雑誌なんかの紹介文になってますけど、どこがやねん、ホンマによう言わんわって感じです。
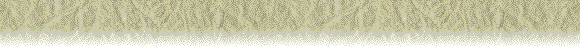

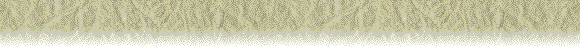


![]()